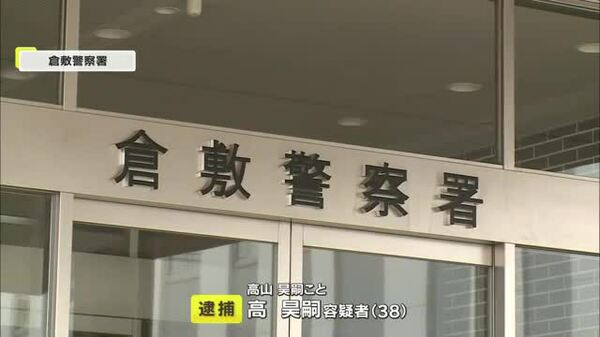A・ほんまけ?
B・茶~しばくけ?
C・おぃえ~
この三つは全て泉州弁(大阪南部の泉州地域で話される方言の一つ)であり、サッと言えて意味までわかるのは、よほど勘のいい人かネーティブな泉州人ぐらいだろう。
ひと口に大阪弁と言っても、かつては「摂津」「河内」「和泉」の三つの国ごとに言葉の言い回しや表現が全然違っていた。
このうち、上方文化の発展とともに広く定着したのが、親しみやすい話し方が特徴の商人言葉である。
その中の一つ、はんなりした「船場ことば」が有名であるが、これは船場商人が京都に出入りするようになって以後、公家社会で使われる言葉の影響を受けたものに堺方言が加わったもの。江戸から昭和の中頃まで船場地域の商家で使われた折り目正しい大阪弁の一種だが、さすがに今の時代「いとはん(長女)こいさん(末の娘)」「かんにん(ごめん)」を日常使いしている人はほぼいないだろう。ひょっとしたら「おはようおかえり(行ってらっしゃい)」くらいは残っているかもしれない。
比較的上品な大阪弁は、現在は大阪市内から北摂にかけての地域で主に使われているようだ。もっとも、北摂の言葉が上品なのは他府県から流入した人が多いためとも言われる。
一方、ドぎつさで有名なのが河内弁や泉州弁。言葉に境界線は無いので、距離的にも近いせいか南河内の河内弁と泉州弁はよく似た表現や言葉が多い。どちらも少々言葉遣いが荒く早口なため、古典的な「喧嘩(けんか)漫才」のようだと言われる。
私は堺で生まれ、泉佐野で育った。泉佐野は母の郷里で親戚も多く、皆な強烈な泉州弁を話す。生活を始めてすぐに私の言葉も泉州弁一色に染まった。そんな人間がプロのアナウンサーになるのだから、人生何があるかわからない。
局アナ、キャスター時代はニュース中心の日々だったので、日頃は正しい日本語を使うよう心がけていたが、原稿を読むこともなくなりラジオパーソナリティーとして個性を全面に押し出すようになってからは、特にサウスオオサカ色が強くなっている。なので、最近私は『共通語、大阪弁、泉州弁のトリリンガルです』と言うようにしている。
明日15日から始まる舞台「じゃりン子チエ」(~25日・大阪松竹座)は、昭和の頃の大阪・西成を舞台にした物語である。他府県の人が聞いても泉州弁のような意味不明感はほとんどないと思うが、それでもネーティブかそうでないかは、聞けばすぐにわかるはず。父方の家が明治・大正・昭和にかけて堺で商売をしていたせいか、私の父の言葉遣いも典型的な堺方言だった。「~やさかい。~でんねん。まんねん」という典型的な大阪商人の言葉。
大阪弁の原型となった言葉を幼い頃から聞いていた私にとって、お好み焼き屋の主人役はとても演技しやすい役柄だ。さすが、わかぎゑふさん(脚本)。こんな話、直接したことなかったが起用してくれるとは…よう、わかってはるなあ!セリフを口にしても肩の凝らない自然体で、大劇場の舞台に初挑戦してきまっさ!
【冒頭クイズの答え】
A・本当ですか?
B・お茶でも飲みませんか?
C・その通りです
(元関西テレビアナウンサー)
◆山本 浩之(やまもと・ひろゆき)1962年3月16日生まれ。大阪府出身。龍谷大学法学部卒業後、関西テレビにアナウンサーとして入社。スポーツ、情報、報道番組など幅広く活躍するが、2013年に退社。その後はフリーとなり、24年4月からMBSラジオで「ヤマヒロのぴかッとモーニング」(月~金曜日・8~10時)などを担当する。趣味は家庭菜園、ギターなど。