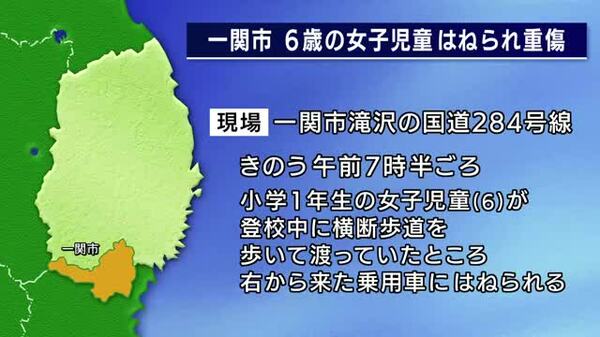ジェンダーをテーマに発信を続ける文筆家「桃山商事」清田隆之代表に聞いてみた
毎週、SNSを中心に話題を呼んでいる火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』(TBS系)。無自覚に男尊女卑的な価値観を抱えるハイスペ主人公・海老原勝男が、恋人の山岸鮎美にプロポーズを断られたことをきっかけに、自分と向き合い始めるという物語だ。
〈こういう人いる!〉と、ネットでは共感者が後を絶たないが、こっそりと「俺もこうだったかも」と胸を痛めた人もいるのではないだろうか?
では、もし自分が「勝男的な部分」を持っていると気づいたとき、何をすればいいのか?
「男らしさ」にまつわる問題をテーマに発信を続ける文筆家で「桃山商事」代表の清田隆之さんに、気づきのきっかけと、そこから変わるためのヒントを聞いた。
男が変わるときはいつも痛みから始まる
――今、ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』が話題です。長くジェンダーや男性の生き方を研究されている清田さんも、やはり注目されているのでしょうか?
清田:はい。以前から原作者の谷口菜津子さんの作品が好きで、これも楽しみにしていました。谷口さんの作品は、いつも「日常の一歩外側」といいますか、我々のすぐ身近にありながら、なかなか気づくことのできない人間模様を描かれているんですよね。ほんの少し角度をずらすことで、それまでなかった新しい景色や希望を見せてくれる作家だと感じていて、このドラマにもそのエッセンスが詰まっているように思います。
例えば、プロポーズを断られた後、一般的な展開であれば逆ギレしたり執着したりしそうなところ、なぜか勝男は料理を始めるじゃないですか。他にも、後輩の白崎くんに「男が弁当作るなんて気持ち悪い」なんて言っていたのに、それからなぜか自分でも弁当を作るようになったり。
マッチングアプリで出会った椿さんとの関係もそうです。恋愛に発展するか、ケンカして終わるか……みたいな展開を予感させつつ、そこから「失恋の傷」を媒介にした友情へと発展していく。この「関係の再構築」がすごく新鮮だなと感じます。しかもそれは決して無理のある描き方ではなく、ちゃんと現実味がある。谷口さんの作品は、そういった部分が本当に魅力的なんですよね。
――勝男はプロポーズを断られたことで自分を振り返り始めました。こうした気づきは、やはり何か大きな出来事がないと生まれにくいのでしょうか?
清田:そうですね……。特に男性の場合、失恋や仕事の挫折、人間関係の失敗、心身の不調など、何かしらのクライシス体験がないと「自分を省みる」ということをしない人が多いのではないかと思います。
例えば勝男だって、キャラクターとして戯画化されているから「ナチュラル男尊女卑マン」のように見えますが、むしろ現実の社会では、彼のような価値観はまだまだマジョリティともいえる。常識や社会規範が味方してくれるので、本人としてはそれが「普通」だと思い込んでいる。それまで問題を感じずにやってこられた分、わざわざ自分を疑うきっかけがない。だからこそ、その日常が揺らぐほどの大きな事件が必要なんだと思います。
――確かに。周りから見れば変わっていても、本人にとっては通常運転ですもんね。
清田:仮に「俺、ヤバいかも」と思う瞬間があっても、具体的な行動や時間の使い方、人間関係まで変えるのは簡単ではありません。勝男のように、過去の自分の言動を見つめ直したり、行動を変えたりするには、相当のエネルギーがいります。ちょっとした意識づけだけでは、なかなか変わるのは難しいですよね……。

勝男が変われた理由は「素直さ」
――気づくきっかけはたくさんあるはずなのに、なぜ多くの人は気づけないのでしょうか?
清田:「気づく」というだけなら、確かにきっかけは無数にありますよね。例えば、育休のニュースを見て「自分は取らなかったな」と思うとか、家事・育児の炎上を見て「うちはどうだっただろう」と振り返るとか。
それが無意味なことだとは思いませんが、気づくだけで解決できるほど現実の問題は簡単じゃないと感じます。
「自分は育休を取らなかったな」で終わらせず、それが原因で実際にどのような問題が起きていたのか、そのことで妻にどんな思いをさせていたのか……というふうに、自分事として具体的に考えていかないとおそらく意味がない。頭で理解するのと、実際に自分の言動と結びつけて考えるのとでは、まったく違うものだと思うので。
――頭では理解していても、自分事として捉えられないと意味がないということですね。気づける人と気づけない人の違いは何でしょうか?
清田:う〜ん、どうなんですかね。自分もまったく偉そうなことは言えないですし、「気づける男は偉い」「気づけない男はダメ」という二元論になっていきそうで怖い質問ではありますが……我々が勝男に学ぶべきところがあるとしたら、それは良くも悪くも「素直である」ということではないでしょうか。
例えば、マッチングアプリで出会った椿さんが、勝男の手作りおでんをコンビニおでんと比べたシーンがあったじゃないですか。心を込めて作ったおでんを否定されたような気持ちになり、椿さんに怒りを向けても不思議ではない場面ですが、そこで勝男は「俺も鮎美に同じことをしてたのでは……」と、自分の過去に引き寄せて考えていく。
後輩の南川さんが好きな「もつ焼き×コークハイ」の組み合わせもそうでしたよね。最初は「合わないでしょ」「あり得ない」と全否定していたけど、さまざまな気づきを経て、実際に自分でも試してみて「これはうまい!」と思い直すに至ります。
気づくきっかけは誰にでもあるけど、それを自分の行動に引きつけて考えられるかどうか。さらにその際、自分の行動や価値観を例外に置かず、実感に沿って真っすぐ見つけられるかどうか。そこに関わってくるのが「素直さ」だと思います。
――原作の設定では、勝男は27歳で大分県出身。年代や地域による違いはあるのでしょうか?
清田:大きな流れとしては、時代が進むほどジェンダー平等は前進しているはずで、古い時代に育った人ほど性別役割に囚われやすい傾向にあるでしょう。私は昭和生まれですが、子どもの頃は専業主婦のいる家庭が一般的で、性別による役割意識もまだまだ色濃かった。
勝男が仮に現代を生きる27歳だとしたら、確かにそのジェンダー観はだいぶ古風なものに映ります。実際に作品でも家族との関係が描かれていきますが、時代背景もさることながら、幼少期を過ごした地域や家庭環境の影響が大きいのかもしれません。
今は共働き家庭が多数派で、パートナーと育児と家事を分担していきましょう、育休もみんな取りましょうという時代になっています。実際に勝男の家族も直面していますが、世の中のジェンダー意識が大きく変化する中で、価値観の板挟みになっている人も増えているのではないでしょうか。

勝男の失敗から学ぶ、見えない偏見が関係に与える影響
――では、偏った価値観を持っていると気づかないまま生活していると、周囲との関係にどんな影響が出るのでしょうか?
清田:例えば勝男の場合、職場では自分の価値観を押し付けて後輩にドン引きされたり、バカにされたりしていました。合コンでも無自覚な男尊女卑的な言動で孤立し、一人だけ一次会で解散。その帰り道に声をかけてきた女性たちとバーに行くものの、そこでも「(勝男の価値観)ヤバいね」と笑われ、早々に帰られてしまいました。
家庭では、パートナーとの関係にヒビが入る可能性も大いにありますよね。勝男のプロポーズ失敗は、偏った価値観に気づかなかった男の、ひとつの末路といえるでしょう。
ドラマの中では後輩たちが直接意見を言ってくれていますが、現実世界では多くの場合、誰も何も言わずに静かに離れていくのが関の山だと思います。しかも本人は自分が男尊女卑的だとは思っていないので、いつまでも理由がわからないままという……恐ろしいですよね。
――友人関係だと、本音を言ってくれる人もいそうですが。
清田:自分と本気で関わってくれる友人であれば、面倒を乗り越えて「お前ヤバいぞ」と指摘してくれるかもしれませんが……でもやっぱりフェイドアウトしていくパターンのほうがリアルですよね。特に、友達であれ仕事仲間であれ、異性の前で男尊女卑的発言をしようものなら、一瞬で線を引かれかねない。しかもグループLINEで噂が広まり、気づいたらみんなから距離を置かれるという状況にもなりかねません。
現実の世界だったら、白崎くんや南川さんは絶対に勝男と関わり続けませんよね。白崎くんは「男が弁当作るなんて気持ち悪い」と言われ、南川さんは料理しないことを窘められました。職場の先輩というだけで、そんなことを言ってくる人と深く関わろうとはしないはずなので……。

七転八倒から始まる、本当の変化
――「自分も勝男タイプかも」と思った人は、何から始めればいいでしょうか?
清田:これまた難しい問いですが……勝男の行動は参考になると思います。勝男は料理を通して、鮎美がどんな気持ちだったのか、自分の言動が相手にどう響いていたのか、リアルに想像して体感する機会を得て、失敗の背景にあったものを自分なりに考えていくわけですよね。
また料理以外にも、後輩に弱みを見せたり、悩みを相談したりもしている。恥ずかしいかもしれませんが、こうした自己開示も大事なプロセスだと思います。
ただ、こうした気づきはクライシス体験があって初めて生じたもの。逆に言えば、そもそも問題を感じていない人が自分の価値観を疑うことはあまりないだろうし、未然に防ぐ方法も正直あるのだろうか……と思えてなりません。
大切なのは、頭だけで理解を得ようとするのではなく、思いっきり落ち込んだり七転八倒したりを繰り返しながら、自分の行動や価値観と結びつけて痛感していくことではないでしょうか。人の痛みがわかるようになるって、やっぱり一筋縄じゃいかないと思うんです。
勝男も、自分で料理を始めてから、顆粒だしやめんつゆのすごさに気づいていきましたよね。かつては「手抜き」とバカにしていたのに、実際に使ってみたら、むしろ味の決め手になると知った。この「予想外の体験を通じて価値観が揺らいでいくプロセス」こそ、変化の本質だと思います。
――変わるのを待つしかないんですね。でも、待ってくれる人はいないんですよね?
清田:悲しいかな、ほとんどの場合は「時すでに遅し」になりますよね……。多分、自分が変わるのを待ってくれるのは自分しかいない。だからこそ、「待つ」というより「自分で自分に付き合う」姿勢が大切なんだと思います。
勝男は、顆粒だしやめんつゆの良さを素直に認め、それを周りに伝えたことで関係が少しずつ好転していきますが、その過程で自問自答を繰り返しているんですよね。そうやって自分で自分を粘り強く支えられたのも大きかったのではないか……。
少しでも「変わりたい」と思うのなら、自分と向き合いながら生活や習慣を少しずつ変えたり、新しいことを試したりしながら、焦らずじっくり自己理解を深めていくしかないでしょう。『じゃあ、あんたが作ってみろよ』は、そういったプロセスの心強い伴走者になるはず。個人的には勝男のファッションが毎回ツボなので、楽しみながらドラマを追いかけていけたらと思っています。
▼清田隆之 1980年東京都生まれ。文筆業、「桃山商事」代表。早稲田大学第一文学部卒業。ジェンダー、恋愛、人間関係、カルチャーなどをテーマに様々な媒体で執筆。著書に『戻れないけど、生きるのだ 男らしさのゆくえ』『よかれと思ってやったのに──男たちの「失敗学」入門』など。女子美術大学非常勤講師。Podcast番組『桃山商事』も定期更新中。