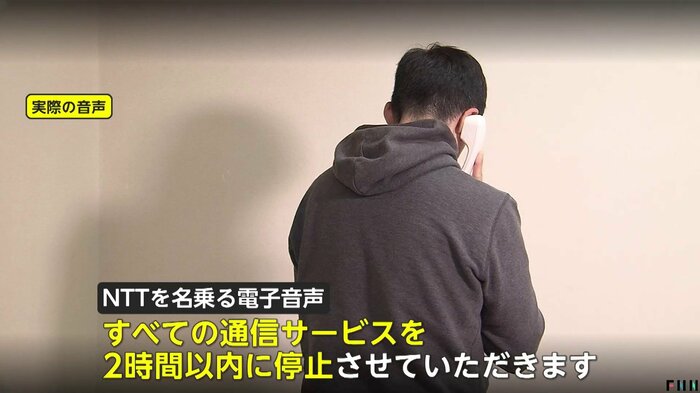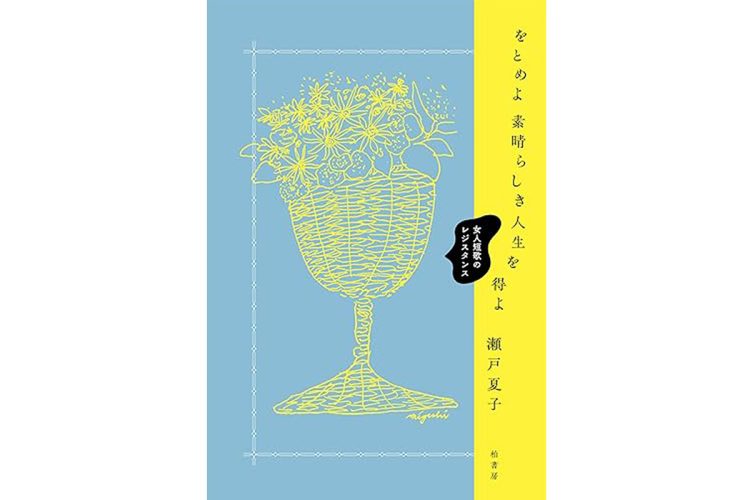
『をとめよ素晴らしき人生を得よ 女人短歌のレジスタンス』/柏書房
【著者インタビュー】瀬戸夏子さん/『をとめよ素晴らしき人生を得よ 女人短歌のレジスタンス』/柏書房/2090円
【本の内容】
《いまこの時代においても切実に必要とされている、あるいはわたしたち自身の姿にもよく似ている彼女たちの物語が存在することによって救われる、あなたたちに向かってこの本は書かれることになる》(「はじめに」より)。1949年に発足した「女人短歌会」。女性歌人たちはどんな人生を送り、どんな苦難を抱えながら短歌を詠んだのか。時代とシスターフッドを丹念に辿ったノンフィクション。
「女性の」と限ると男性は「関係ない」と思ってしまう
『をとめよ素晴らしき人生を得よ』は、戦後まもない1949年に結成された「女人短歌会」と歌誌「女人短歌」を軸にして、彼女たちのシスターフッドと闘いを、2人ずつの関係性を通して積み上げるように歴史を描く、すぐれたノンフィクションである。
著者の瀬戸さんは歌人で批評家でもある。編集者の注文は、「女性の短歌の歴史について書いてほしい」というものだったそう。
「ありがたいご依頼ですけど『女性の』と限ってしまうと男性は『自分には関係ない』と思ってしまうかもしれない。男性の短歌史がメインで女性がサブというふうにはしたくない。女性たちのグループである『女人短歌会』を提示して、こういう活動がありましたというアプローチをとるほうが、短歌界全体にとってもいいんじゃないかと思いました」
第1章で取り上げたのは、大西民子と北沢郁子という、短歌にくわしい人でないとおそらく名前を知らないであろう歌人のペアだ。なぜこの2人から始めようと思ったのだろう。
「シスターフッドをこの本のテーマにすると決めていて、『女人短歌会』のメインといえるシスターフッドは葛原妙子と森岡貞香なんですけど、さすがに頂点を最初に持ってくることはできない。いろいろ考えたときに、シスターフッドという本の枠組みを一番わかりやすく提示できるのがこの2人でした」
かたはらにおく幻の椅子一つあくがれて待つ夜もなし今は
大西民子
帰らない夫を待つ妻の思いをうたう大西と、彼女が描くのとは異なる大西の姿を描いた北沢。情愛にあふれながらも時に切り結ぶ、親友2人の複雑な関係性を複雑なままみごとに描き出す。
「どうやったら面白く読んでもらえるかというのはすごく考えました。一般的に知られていない歌人をもっと知ってほしい気持ちもあるし、芥川龍之介とか著名な名前も少しは出しておかないと読む側からしたらしんどいかもしれないですし。
芥川龍之介や彼の恋人と言われた片山廣子、齋藤瀏(二・二六事件にかかわったとして逮捕された陸軍少将)の娘である齋藤史など、よく知られた人物の場合は既存の物語の枠をいったん外して新しい視点でこういう読み方もできると提示しました。逆に存在そのものがあまり知られていない場合はいったん物語化する書き方を選んでいます。それによって、読んだ人が別の意見を持ってまた別の物語を提示してくれたらいい」
大西と北沢の物語もそうだし、「女人短歌」のプラットフォームをつくった、第4章の北見志保子と川上小夜子の関係性も非常に印象深い。
北見と川上は、「女人短歌」の前にも1925年に「草の実」という女性の歌誌を立ち上げている。その後、北原白秋が主宰する「多磨」に加わるが、もう少し広い世界で活動してみたいと申し出た北見が、白秋の逆鱗に触れ除名される。川上はただ1人、北見とともに「多磨」を退会し新しい歌誌を立ち上げる。連帯して闘った友の最期をしるす北見の文章は美しく胸にのこる。
『乳房喪失』の歌人中城ふみ子と中井英夫、釈迢空(折口信夫)と弟子の穂積生萩のように、女性歌人と男性編集者や師との関係性が、シスターフッドの観点で論じられているのも興味深い。
「今まであまり言われてこなかったですけど、葛原妙子を評価した塚本邦雄もクイア的な感性を持っていて、女性短歌が世に出るうえでクイア男性が果たした役割は大きいです。
中城ふみ子と中井英夫の関係が私はすごく好きで、絶対書こうと思っていましたし、釈迢空は『女人短歌』の思想的支柱なので彼のことも書くと決めていました。誰と書こうか考えているときに浮かんだのが穂積生萩です。生萩はキワモノという扱いだったり、折口関連の本の参考文献からも外されていたりするんですが、歌に関しては迢空のすごくいい部分を受け継いでいます」
もとの身は雨乞いシャーマン・アマタラス死して慈雨ありぬ やるやおまへんか
穂積生萩
昭和天皇崩御の雨の日に詠んだ歌からは、確かに瀬戸さんが言う「異様なまでの自由さ、天衣無縫さ」を感じることができる。
タイトル「そしてあなたたちはいなくなった」を変えた訳
第一部の終わりに「補章」として「アガサ・クリスティーと中島梓」という、短歌とは一見かかわりのなさそうな章が設けられている。
「私が評論を書くうえでいちばん影響を受けたのが中島梓で、何の話をしても中島梓の『小説道場』の話になってしまうというところもあるんですけど、女性同士の文学のコミュニケーションの場として『小説道場』はすごくうまい成立の仕方をしていたので、この章を入れました」
巻末には、瀬戸さんが10首ずつ選んだ、本文に登場する歌人のアンソロジーを収めた。
印象的でうつくしいタイトルは、葛原妙子の歌から。
早春のレモンに深くナイフ立つるをとめよ素晴らしき人生を得よ
「ウェブで連載していたときは、『そしてあなたたちはいなくなった』というクリスティーの『そして誰もいなくなった』をもじったタイトルでした。5年前ならそのまま受け入れられたと思いますが、今はマイナスイメージでとらえられるかもしれないと思い、変えました。『を』から始まる本のタイトルはなかなかないので、目立つところもいいんじゃないかと思います」
【プロフィール】
瀬戸夏子(せと・なつこ)/1985年石川県生まれ。歌人、批評家。著書に、歌集『そのなかに心臓をつくって住みなさい』『かわいい海とかわいくない海 end.』、評論集『現実のクリストファー・ロビン 瀬戸夏子ノート2009-2017』『クリスマス・イヴの聖徳太子』、歌集ガイド『はつなつみずうみ分光器 after 2000 現代短歌クロニクル』など。
取材・構成/佐久間文子
※女性セブン2025年11月6日号